教職員紹介
- 絞り込み検索
- ブランディングデザイン
- グラフィック
岡野 隆次 Takatsugu Okano

株式会社 大広 大阪本社 国内グループ統括局
アカウントディレクター
広告からクリエイティビティの時代に―。広告は、創造性や想像力を無くしては成り立たなくなりました。メディアは飽和傾向にあり、デジタル系サービスも新市場でなく普通のサービスになりつつあります。広告のもとは、物売りの発信する声であったり音色であり、人の心をとらえることでありました。いつの時代も人を動かすのは情緒と役に立つ情報です。デザイナーにとって広告とは、広告情報に触れる感情生活者に感動を与えること。広告を美術館と思い、署名を付ける気持ちで作品を創ってほしいです。

- ブランディングデザイン
- グラフィック
- イラストレーション
山下 昌彦 Akihiko Yamashita
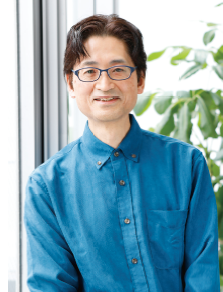
フリーライター
音楽関連本を中心に著書16冊を出版
SoftBankコンテンツ番組の執筆
webデザイン制作
インディーズバンドのプロデュース
宝塚歌劇団関連本や、ドキュメンタリー写真集などの編集
デザイナーは究極のサービス業。ユーザーに夢と感動を与え、あなたの仕事に関わった人すべてを幸せにする。新しい時代の扉を開いて、見たこともない世界を人々に見せていくのもデザイナーの仕事です。デザインというボタンをひとつクリックするたびに、発見と驚きにつながっていく。簡単そうだけど奥が深いです。デザインは完璧と100%のない世界。でもイメージしてください。あなたの作った物で誰かが笑顔になる。それはすごくステキで大切なこと。そんな小さな一歩から始めてみましょう。
- マーケティングデザイン
上野 リサ Ueno Lisa

株式会社Answer
代表取締役社長 デザイナー
JAGDA・HADC正会員
私のミッションは「成長を望む方にデザインとスキルを提供し共に歩む。」
大阪、中国エリアを拠点に学校、企業のデザイン、EC・WEBコンサルに携わっています。行政やソフトバンク株式会社とコラボし600社以上のIT伴走支援事業を実施。学生はじめリスキリングを含む1000人以上に育成指導。マーケティングデータに基づいたデザイン指導を行っています。
■2024年文部科学省より取材「#知る専」出演。
■大阪万博ヘルスケアパビリオンVR撮影プロデュース。
https://youtu.be/jfMwv4an6Oc?si=X_k1rRevZCVJtTCN
- ブランディングデザイン
- プロダクト
杉山 陽二 Yoji Sugiyama
サン・デザイン・プロダクツ 代表取締役
釣具、化粧品メーカを経て’82年4月に独立、日用生活品、家庭電気調理器具等の
製品企画・デザイン制作を業務としたデザイン事務所を起業、現在に至る。
有限責任事業組合「生活を快適にするものづくりの会」理事、
愛知産業大学大学院教員、日本デザイン学会評議委員
これからデザイナーをめざす学生は、超高齢社会・環境保全型社会のもと、高齢者・障がい者、また環境・健康に配慮したものなど、人間を中心とした商品の開発をしていくことが重要です。また、デザインを学ぶにあたり、それが果たしてきた社会的・文化的な役割や上述の社会背景など多様な視点からデザインについて考察し、分析することも重要となります。さらに、商品企画、デザインマネジメント、ブランド戦略など、今後拡大するデザイナーの職域についても勉強していかなければなりません。
- ブランディングデザイン
- インテリア・空間デザイン
北山 あけみ Akemi Kitayama
インテリアデザイン、設計、制作(ガラスアート・ミラー・照明・オブジェ家具等)
講座・講演(インテリア・色彩心理・パーソナルカラー・造形・芸術環境分野)
「デザイン」の本質とは何でしょう?さまざまな学びを通し、その答えを探究してください。「美」は常に再生しています。花が咲き実をつけて種となり、生まれ変わるように。デザインは環境によって大きく変化します。表面的ではなく内面が感じられるもの、人々の眼にどう映るのか、心に訴えるデザインとは、どのようなものなのでしょう?五感をフルにはたらかせて「感性」をとぎすまし、「知性」に裏づけされた「デザイン力」を表現できるよう応援します。
- ブランディングデザイン
- グラフィック
- イラストレーション
田中 浩伸 Hironobu Tanaka
クリエイティブディレクター
デザインを小ぎれいに、プロのように仕上げる。そんな固定観念の中で小さくまとまったアイデアや作品を、今は創るべきではないと思う。いかに意表を突くか。ハッとさせるか。はみ出したっていいし、マジメにはっちゃけるならそれもいい。デザインの専門学校に通う今しか体験できないことに挑戦して欲しい。自分でリミッターをかけないで、今こそ伸びしろを大きく豊かに蓄えるとき。私も本気で応えていきます。
- ブランディングデザイン
- グラフィック
下東 英夫 Hideo Shimohigashi
エアーズ 代表
劇団、公共ホールの公演チラシ、ポスター・リーフレットなどのAD。
店舗、企業のシンボルマーク、ロゴのデザイン・出版企画、編集デザインなど
商品企画から広告のデザインまでを1 人のデザイナーがトータルでディレクションするケースが増えています。さまざまな事柄を、デザインから解決しようとする動向もみうけられます。こういった時代に、デザイナーとして仕事をしていくには、デザインの表現技術を修得するだけでは不十分です。何を学べばいいか?社会的な教養はもちろん、社会に対するデザインの役割を認識、理解し、何に対てデザインは有効な手段になりうるかを学ぶことが重要です。問題解決に対するデザインコンセプトのたて方を学んでください。そうすることが将来、デザイナーとして活躍できるあなたの強力な「デザイン力」になると確信しています。
- ブランディングデザイン
- グラフィック
木村 正喜 Masaki Kimura
キャスト・コミュニケーションズ 主宰
コピーライター・プランナー
ズシリと重い辞書をパラパラとめくっていて、思わずポンと膝を打った。『創』の右側の「りっとう」は“刀”のことで、創という漢字には“傷”や“はじめる”という意味もあるらしい。木のかたまりに切れ目をつけて、そこからザクザクと彫刻なんかをつくっていくイメージだろうか。「失敗するかも…」とためらったり、指を切ったりすることもあるけれど、最初の切り出しがないと木は作品に生まれ変わらない。そして、創るおもしろさに、人はいつしか不安や痛みを忘れている。創造力という刀の初めのひと振り、まずそこから始めてみよう。
- ブランディングデザイン
- グラフィック
渡壁 光温 Mitsuharu Watakabe
DMI Power Studio 代表
プロデューサー・映像ディレクター
インターネットやマルチメディア、デジタルという言葉に関するモノづくりは、コンピュータの前で孤独に格闘しているイメージがある。確かにそうなんだが、表現したいアイデアを得るには、結局はいろいろなモノを見に行き、さまざまな人と出会い、会話し、体験することになる。表現はたとえデジタルコンテンツであっても人との交わりであることに変わりない。時に苦悩し、それがゆえに苦労の果てに喜んでもらえたりすると胸が熱くなる。きわめて人間くさい活動だということだ。
- ブランディングデザイン
- インテリア・空間デザイン
岩尾 美穂 Miho Iwao
オフィスいろどり
広告代理店の企業営業を経て独立。各種専門学校、
企業研修にて色彩学、色彩計画、
カラーマーケティング等の授業・講座を担当。
A・F・T1 級色彩コーディネーター、東京商工会議所1 級カラーコーディネーター(環境色彩)
執筆・編集協力:Color of Life 〜生活に色を取り入れよう〜(税務経理協会出版)
色彩検定対策テキスト2級/3級(税務経理協会出版)
「好奇心」を持っていますか?インターネットにアクセスすれば世界中の情報を瞬時に得ることができる現在、与えられることに満足をしていませんか?本を読みましょう。街を歩きましょう。人と関わりましょう。身体中をアンテナにして多くの刺激を受けることで視野が広がり、学校での学びの時間がより有益な時間となることでしょう。「好奇心」に導かれて色を生業とした私からは、物質的に満たされた生活の中でますます重要な役割を担う「色彩」の視点から、皆さんの好奇心を刺激していきたいと思います。







